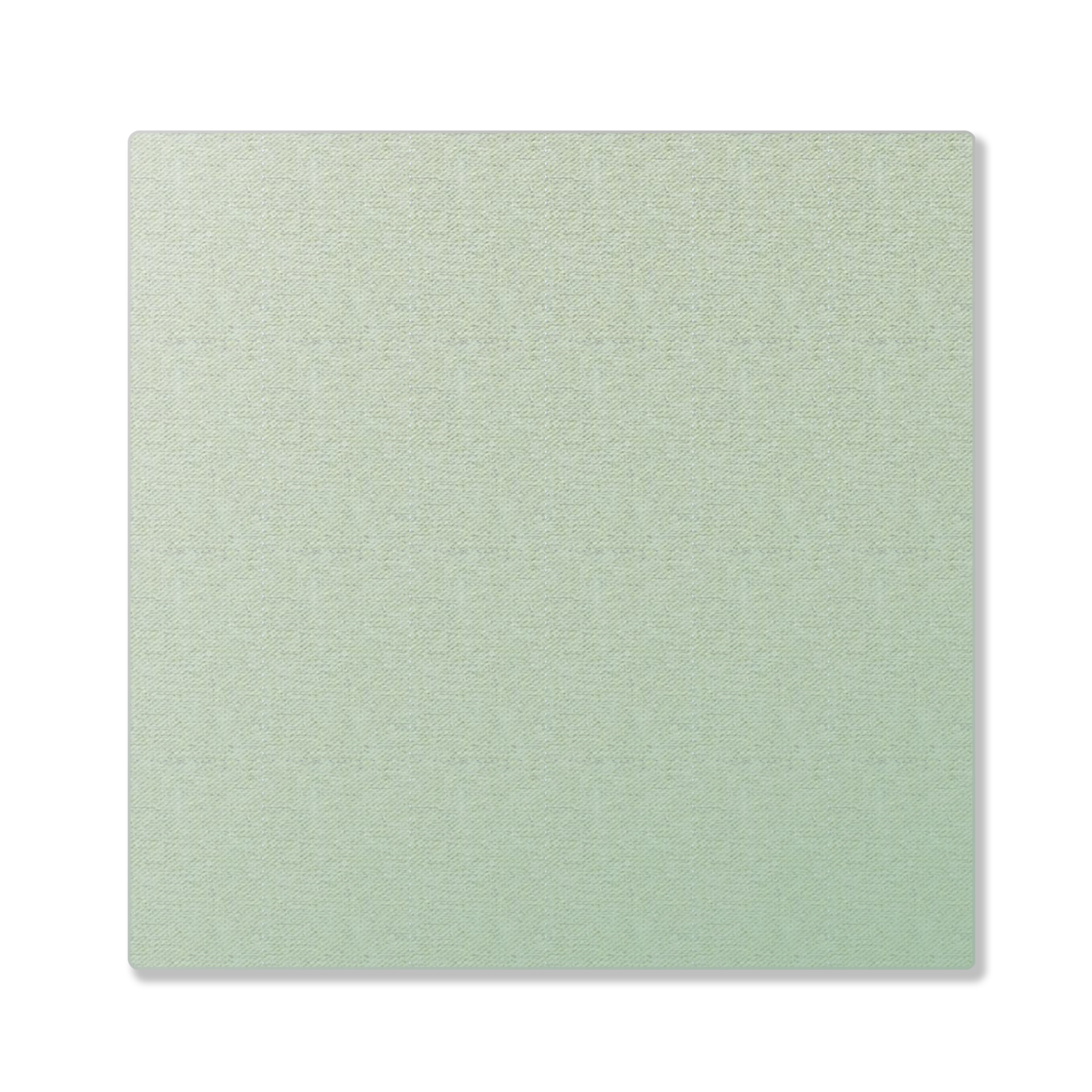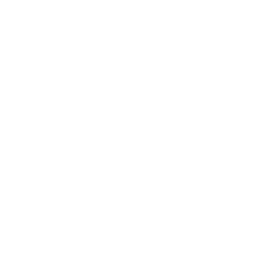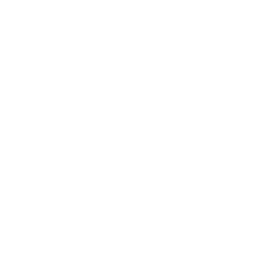難聴のリスクを生む危険な騒音

騒音性難聴は、私たちの生活において深刻な健康問題となり得る無視できないリスクです。特に大きな音に繰り返しさらされる職業に従事する人々にとって、この問題は耳を守るための重要なテーマとなります。この記事では、騒音性難聴がどのように発症するのか、どの職業がリスクにさらされやすいのか、そして予防するための効果的な方法について詳しく解説します。
騒音性難聴とは

騒音性難聴は、音響性聴器障害とも呼ばれます。音にさらされることで生じる難聴であり、主に急性と慢性の2種類がある特徴です。以下にポイントをまとめます。
- 急性音響性聴器障害:爆発音やコンサートなど強大な音を受けたときに発症しやすいです
- 慢性音響性聴器障害:日常的に騒音に触れ続け、数年かけて徐々に進行します
初期に気づけない場合も多く、「C5ディップ」と呼ばれる4000Hz付近の聴力低下が特徴です。早めの予防と検査が重要になります。特に仕事場などで騒音にさらされる方は定期的な聴力検査を受けると安心です。これらに気を配り耳を大切にすることを心掛けましょう。
騒音性難聴になりやすい職業

騒音性難聴は、一般的に工事現場の作業員や鉄道業界従事者、航空業界のスタッフなど、85dB以上とされる大きな音に長時間さらされる職業に多く見られるため、「職業性難聴」とも呼ばれています。これらの職業では、大型の機械や交通機関が日常的に発する大きな音にさらされるため、聴力への影響が避けられないことがあります。
一方で、爆発音や炸裂音、さらにはロックコンサートでの強烈な音響のように、120~140dBといった非常に大きな音に短時間でさらされることによって引き起こされる難聴は、「音響性外傷」と呼ばれます。このタイプの聴覚障害は、突発的に発生する強烈な音によって一時的または永久的に聴力が損傷されることから、特に注意が必要です。音響性外傷は、意識的な予防策や防音対策、耳栓の使用などにより、そのリスクを大幅に軽減できるとされています。
騒音性難聴をどのように確かめるか?

医療機関で聴力検査を行った際、25dB以上の音が聴き取りにくい場合は、軽度の難聴と診断されます。40dB以上になると中等度の難聴とされ、このレベルでは1m離れた場所からの大声がかろうじて聞こえる状態です。さらに、60dB以上の音が聴き取りにくくなると高度難聴とされ、耳元で大声を出さないと聞き取れない状況にあります。
日常生活では、家族や職場の人たちが話しかけても反応がない場合、周囲の人が耳鼻咽喉科への受診をすすめることがよく見られます。聴力の低下はコミュニケーションを取りにくくする恐れがあるため、少しでも聴こえにくさを感じたら早めに受診することが重要です。
騒音性難聴にならないためにはどうすれば良い?

騒音性難聴は、一度発症すると効果的な治療法がないため、難聴自体を治すことができません。そのため、予防が最も重要な対策となります。防音保護具として耳栓などを使用し、耳を保護することが基本的な予防策です。また、騒音環境を改善するための手段として、吸音パネルを使用することで室内の音環境を向上させることができます。
特に継続的に音が反響する部屋では、音が反射することによって音量が増幅されるため、音響環境の悪化につながります。対策方法の一つとして、吸音パネルを設置することにより、反響音を吸収し音量を軽減することが可能です。これにより、過剰な音によるストレスを減少させることができます。
LcycLでは、通常のグラスウールやフェルト素材と比べて、吸音性能に優れるウレタン素材を使用した吸音パネルを提供しています。吸音パネルを導入することによって、職場や家庭の音の問題を軽減し、より快適な音環境を構築することが可能となります。騒音対策を求める方には非常におすすめできる製品です。
- 9,350円 [税込]
【吸音】と【寝床】の2WAY仕様「やわらか吸音パネル」 クラウドファンディングサービスMakuakeにて「思いやり吸音パネル」と題してプロジェクト掲載しました。 壁に取り付ければ吸音パネルとして室内騒音を低減し、取り外せばクッションマットとして使用できます。ご自宅の居住環境の改善にご活用下さい。 自動車部品に採用されているウレタンの端材・廃材を一部再利用しており、環境に配慮したアップサイクル製品です。 【商品特徴】 ・吸音性能の高いウレタンを中材に使用 最大約20dBの騒音低減効果(独自…
まとめ
騒音性難聴は、発症すると根本的な治療法がないため、日常生活での予防が何より重要です。耳栓や吸音パネルなどの対策を講じることで、身近にある騒音から聴力を守ることができます。適切な対策を取り入れて、日々の生活で耳を大切にすることが、騒音性難聴のリスクを軽減し、音に満ちた生活の質を向上させるためのカギとなります。どんな小さなサインにも気を配り、早期の受診や対策を心掛けましょう。